不動産登記法③
不動産登記法について
この記事で所有権、表示、変更の登記について勉強したね!
今回は、仮登記、相続や継承、合筆・分筆、登記官などについて勉強しよう
仮登記
仮登記とは、登記申請に必要な書類がそろわない場合や、買主がまだ所有権を得てはいないが、将来、その物件を保有する「予約者」としての権利を得る場合などにその優先順位を確保(順位保全)するために行う登記のこと。
仮登記 とは | SUUMO住宅用語大辞典 より引用
登記義務者の承諾
仮登記は、仮登記の
登記義務者の承諾があるときは、当該
仮登記の登記権利者が単独で申請することができる(不動産登記法107条1項)。
第三者の承諾
所有権に関する
仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該
第三者の承諾があるときに限り、申請することができる(不動産登記法109条1項)。
仮登記の抹消
権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない(不動産登記法60条)のが原則だが、例外的に
仮登記の抹消は、
仮登記の登記名義人が単独で申請することができる(同110条)。
相続・承継・代理
相続人と一般継承人
表示の登記
所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、
相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる(不動産登記法30条)。
相続や承継した人が登記できなかったら、不便そうだよね
区分建物の表題登記
区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、
被承継人を表題部所有者とする当該建物についての
表題登記を申請することができる(不動産登記法47条2項)。
相続や承継した人が自分の物と証明(表題登記)できるんだね!
代理
民法111条の場合と異なり、登記の申請をする者の委任による
代理人の権限は、
本人の死亡によっては、消滅しない(不動産登記法17条1号)。
不動産登記においては、相続・承継・代理した場合本人が死亡したときも継続して登記できるんですね
合筆・分筆
合筆
合筆とは、隣接する数筆の土地を1つの筆の土地に、法的に合体させること。所有者が登記所に「土地合筆登記」を申請することで認められる。合筆後の土地の地番は最も若い地番となり、合筆した土地同士を隔てていた筆境界線は抹消される。
合筆 とは | SUUMO住宅用語大辞典 より引用
登記名義人が異なる場合
表題所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない(不動産登記法41条3号)。
不動産登記法は、公示の簡明化のため、土地につき「筆」を単位として公示するものとし、所有権についての権利関係が異なる土地相互の合筆登記を認めないのです。
なお、合筆の登記ができる場合、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない(同法39条)。
分かりやすくするために、その土地を持ってる人が合筆できるんだね
所有権がない場合
所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記は、することができない(不動産登記法41条5号)。
分筆
分筆とは、「一筆」として登記されている土地を数筆に分けて土地台帳に登記し直すこと。「一筆」とは、土地の個数を示す登記簿上での単位のことで、登記簿では一筆の土地ごとに1つの用紙を備えることになっている。土地を分筆すると、分筆後、新しくできた土地には新たな「地番」が付けられる。
分筆 とは | SUUMO住宅用語大辞典 より引用
分筆できる?
分筆された土地の甲区及び乙区には、元の土地の登記内容が職権で転写される(不動産登記則102条、不動産登記準則74条)。
所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地についても分筆の登記をすることができます。
ちなみに、所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について制限されているのは、合筆の登記です。
登記官・官庁など
登記官とは、登記に関する事務を処理する権限を持っている法務局に勤務する法務事務官(公務員)です。登記所(法務局)における事務は、すべて登記官の責任で取り扱われます。
登記官とは? | AnaMachi (to-ki.jp) より引用
登記官
登記識別情報の通知
登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令の定めるところにより、速やかに、当該
申請人に対し、当該登記に係る
登記識別情報を通知しなければならない(不動産登記法21条本文)。
債務者Aが債務者Bに代位して所有権の登記名義人CからBへの所有権の移転の登記を申請した場合において、当該登記を完了したときは、登記官は、
Bに対し、当該登記に係る登記識別情報を
通知しなければならない。
本問では、債権者Aが債権者代位権を行使してBの登記を申請しているので、登記申請人として扱われるのは債務者Bです。
登記の却下
申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた
登記所の管轄に属しないときは、登記官は理由を付した決定で、
登記の申請を却下しなければならない(不動産登記法25条1号)。
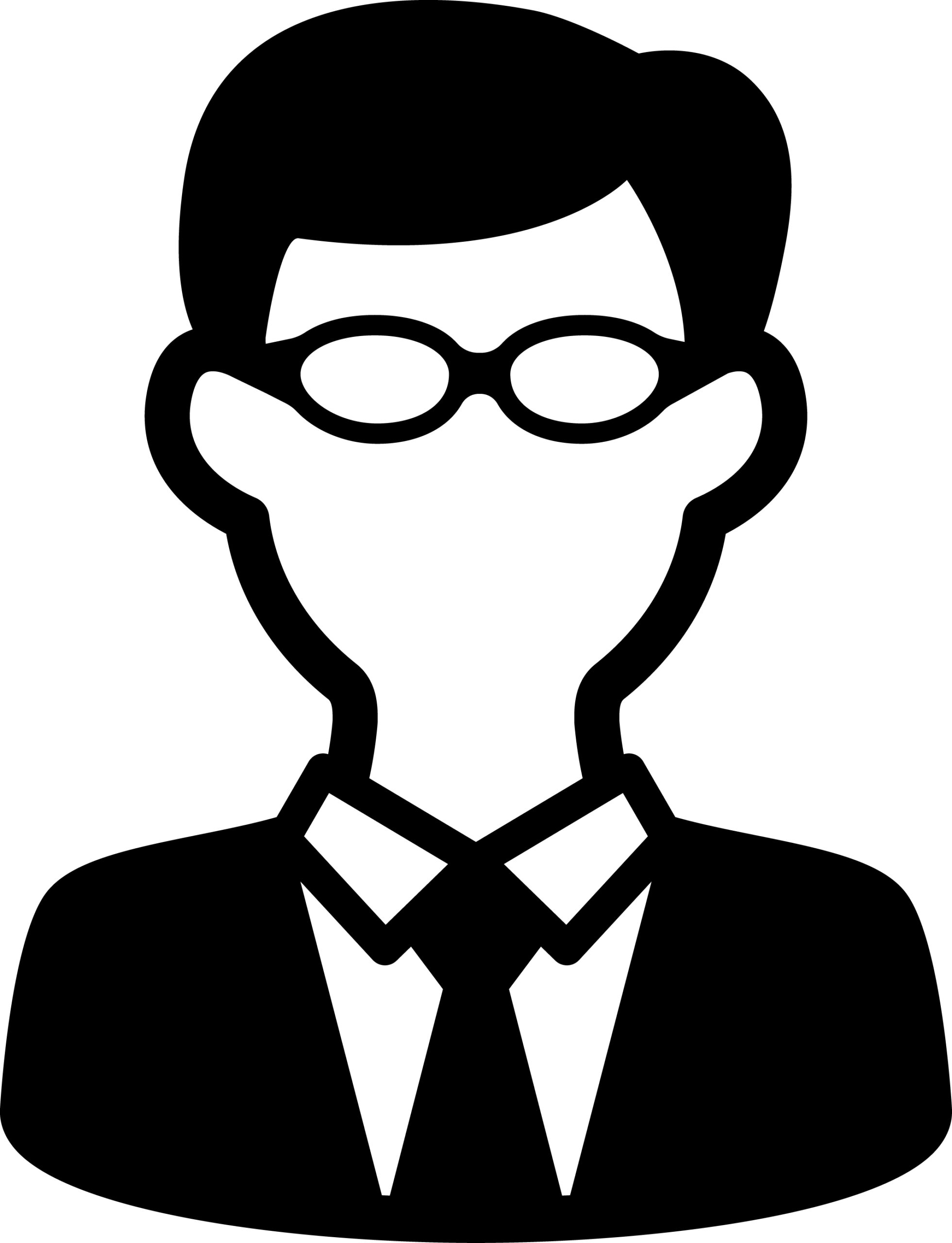
登記官
分筆の登記
分筆又は合筆の登記は、表題所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない(不動産登記法39条1項)。そして、
登記官は、上記の申請がない場合であっても、一筆の土地の一部が別の地目になったとき、又は地番区域を異にするに至ったときは、職権で、その土地の
分筆の登記をしなければならない(不動産登記法39条2項)。
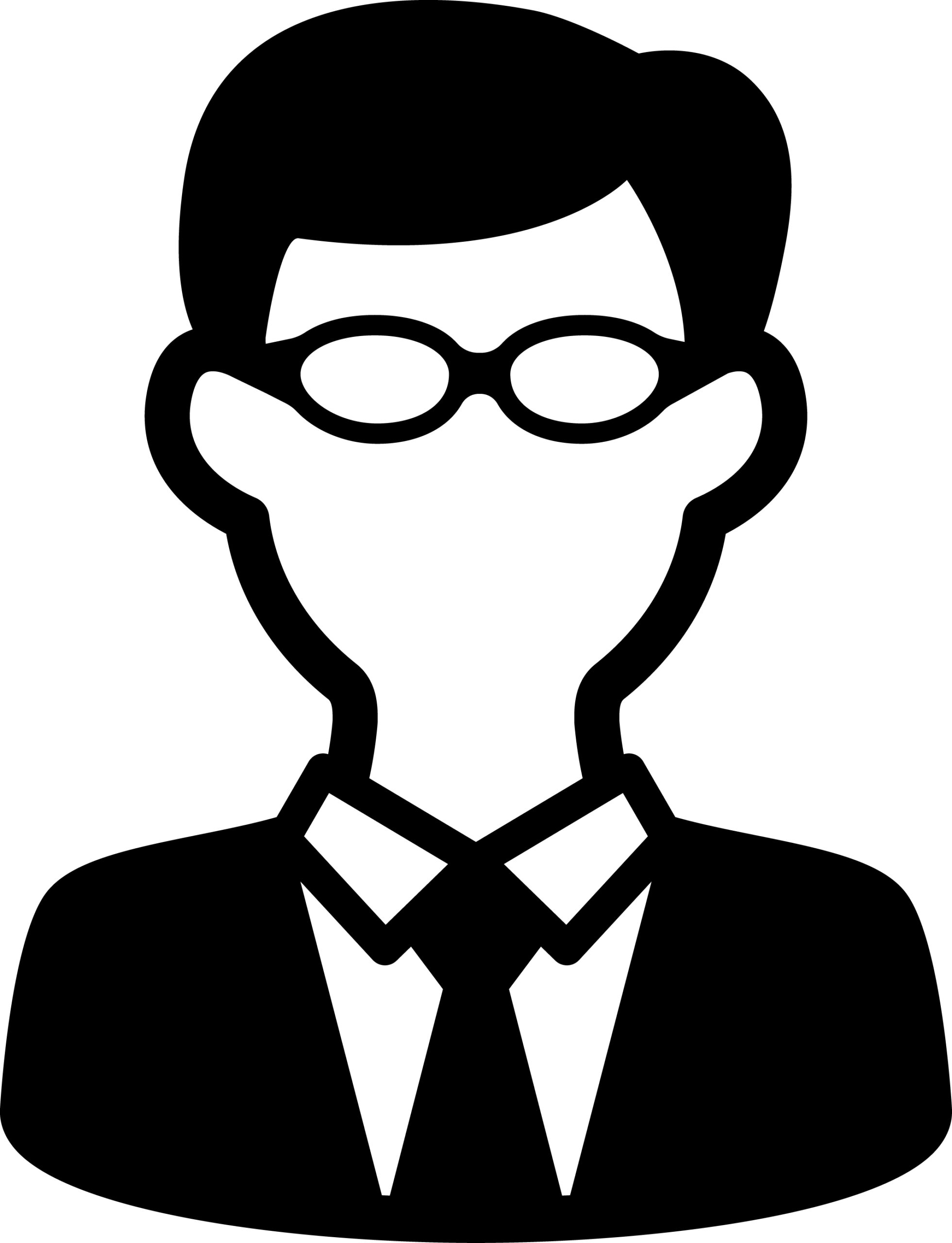
登記官
土地が別れたら、分筆の登記をしなければならないんです
土地については、「筆」を単位とすることから一筆の土地については、同じ地目でなければならないためです。
表示の登記
表示に関する登記は、登記官が職権ですることができる(不動産登記法28条)。
官庁・公署
登記は、法令に特段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない(不動産登記法16条1項)。
当事者じゃなくても、官庁や公署の嘱託があれば登記できるんだよ!
最後に

宅建 過去問 2021 - 一問一答と10年分の過去問演習アプリ
Trips LLC無料posted withアプリーチ

















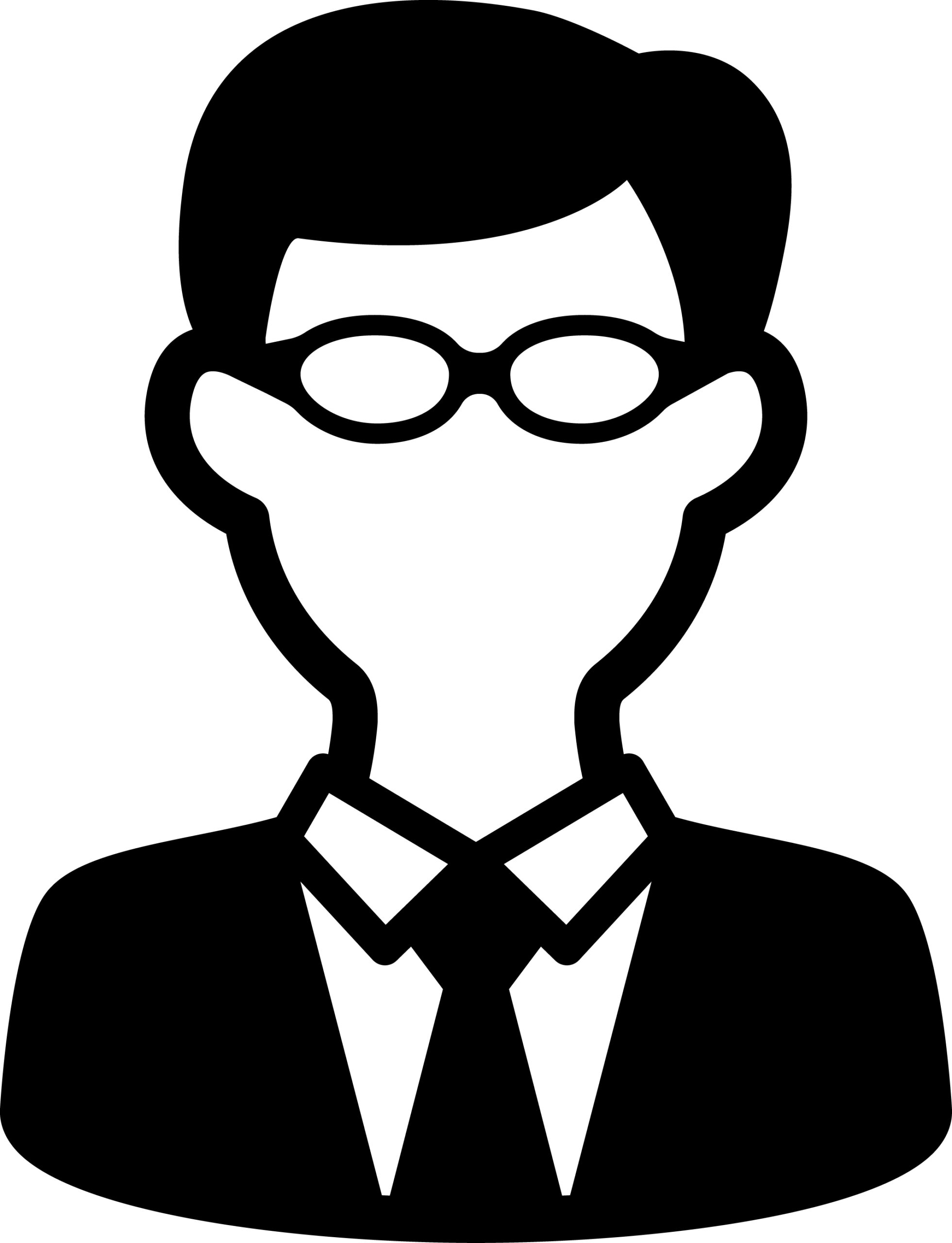
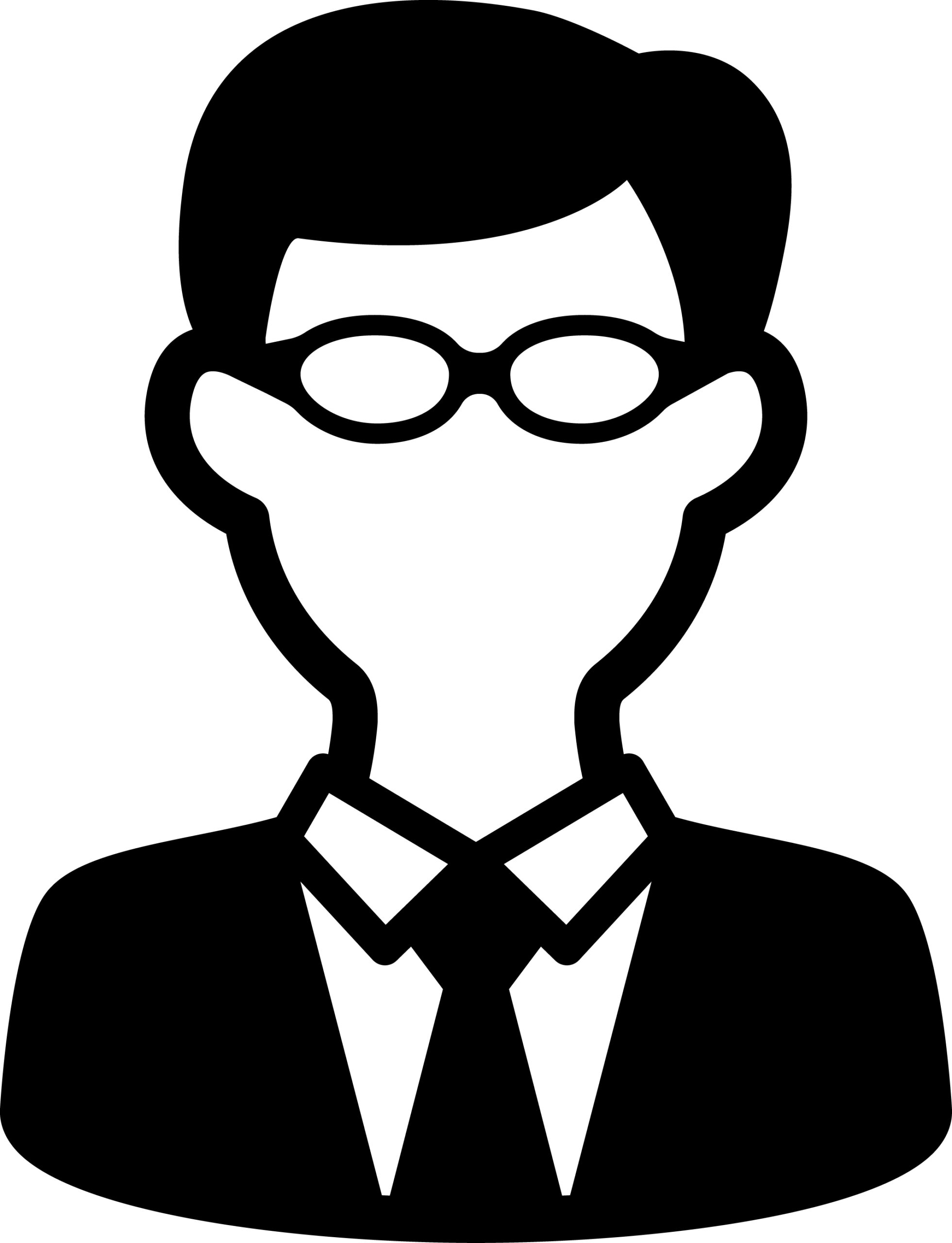



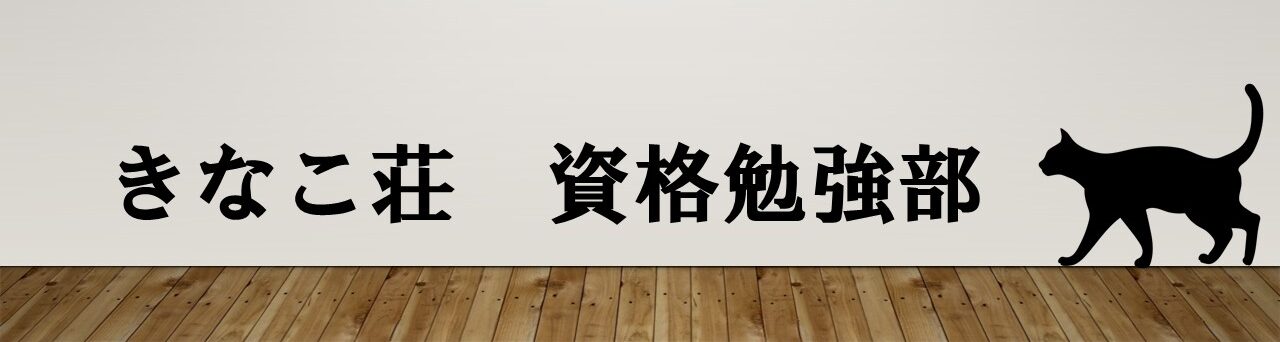
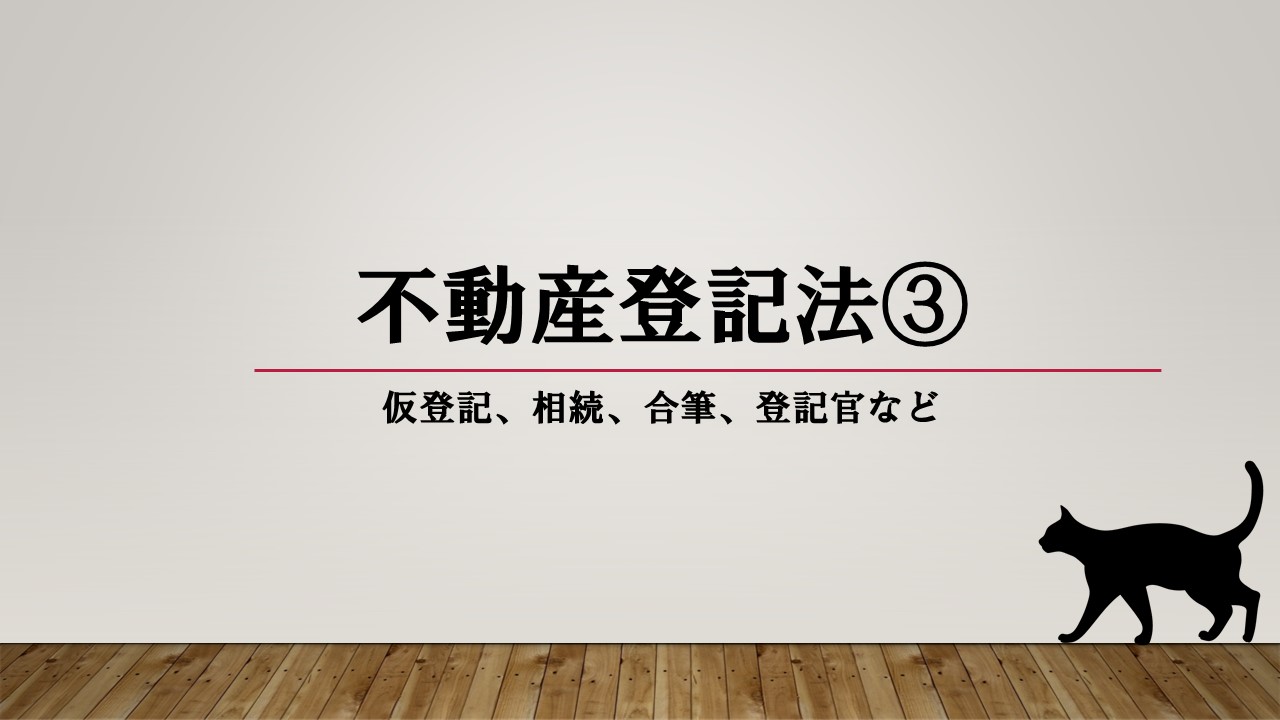






コメント